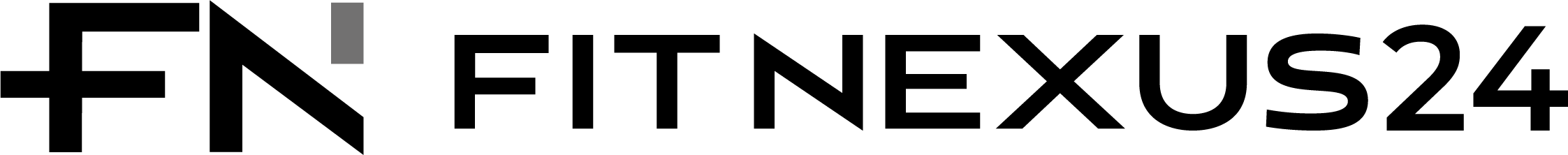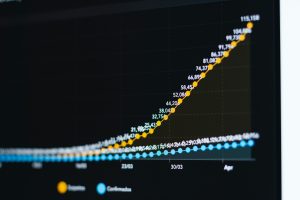フィットネス業界に通用しない「駅前信仰」──商圏分析の落とし穴

商圏分析は、店舗型ビジネスにおいて避けては通れない。 GISやAIの進化により、分析手法は高度になり、取得できるデータは爆発的に増えた。だが、その進化は皮肉にも「何を分析すべきか」を見えにくくしている。
今、必要なのは分析力ではない。自らのビジネスがどういう構造で成り立っているかという、設計図を持っているかどうかだ。それがなければ、商圏分析は精緻な数字を弄ぶだけのゲームに堕する。
フィットネスという会員制業態は、その極端な例である。「駅前=正義」「人通り=集客」といった他業種の常識は、ここでは通用しない。では、信じるべきロジックは何か。本記事では、その答えを探る。
商圏分析の進化とその落とし穴
商圏分析はここ数年で劇的に変化した。かつては紙の地図と国勢調査が頼りだった分析が、今ではjSTAT MAPをはじめとしたGISツールや、AIによる予測モデルによって誰でも高度なデータを扱えるようになった。しかも、POSデータやGPS、SNSの位置情報といった“動的データ”まで手に入る。分析できることは飛躍的に増えた。

だがその進化は、「使いこなせる前提」を持たない人間にとっては、むしろ“混乱の温床”となる。ツールの性能に比例して、何を見ればいいのか、どの数値が自分のビジネスと関係するのか、見えなくなる。選択肢が増えることで、判断は鈍くなる。
重要なのは、「どのツールを使うか」ではない。「どんな仮説を持って、どんなロジックで、何を確認したいのか」である。
「仮説なき分析」が陥る空虚
よくあるのが、「使えるデータを全部集めたが、結局どう活かせばいいか分からない」という状態だ。jSTAT MAPで地域の人口構成を調べ、有料ツールで人流や昼夜間人口まで把握しても、そこに仮説がなければ意味を成さない。
たとえば、「この地域には若年層が多い。だから低価格帯のプランが刺さるはずだ」といった仮説があれば、データの解釈には方向性が生まれる。しかし、「AだからBである」という程度では、どれほど詳細な情報も単なる“情報”で終わり、現実的に集客・売上に接続されることは稀である。
仮説を立てるという行為は、自らのビジネスを言語化することに等しい。商圏分析の前に、それができていなければ、どれほどの精度で地図を塗っても、得られるのは「地図を塗った事実」だけである。
データは目的に従属する
すべてのデータは目的に従属する。それが商圏分析の大前提である。
目的を見失えば、データは“意味”を失い、“数字”としてしか残らない。
たとえば、1回購入型の物販と、会員制のフィットネスとでは、商圏の捉え方はまったく異なる。前者ならば通行量や視認性が効くかもしれないが、後者にとっては「日常動線への組み込みやすさ」が鍵となる。
その違いを踏まえたうえで、「この事業のターゲットは誰か」「その人たちはどこから、どの手段で、どの頻度で来るのか」という想定を持っていなければ、データの選定も評価もできない。
商圏分析は、決して“地理の話”ではない。
それはビジネスの構造そのものを、空間と時間に投影する作業である。
その構造が見えていなければ、いかなる統計も、意味を持たない。
フィットネス業界における「例外の常識」
フィットネスは、商圏分析の“通説”が通用しにくい業界である。
人通りの多さや駅からの距離といった一般的な指標が、必ずしも集客に結びつかない。
むしろ「なぜそこに通うのか」「どうやって生活に組み込まれるのか」という“行動の文脈”こそが成否を左右する。
たとえば、駅前の一等地に構えた高額テナントの店舗よりも、郊外の住宅地にある駐車場付きのロードサイド型店舗の方が会員数が多い、また同一ブランドでの会員数ランキング上位は郊外型店舗が常連であるケースは珍しくない。
この現象は、もはや“例外”ではなく“常識の逆”である。
フィットネスという業態は、「習慣化」が命である。
週に複数回、無理なく通えるかどうか。
仕事帰り、休日の朝、家族との買い物ついで──生活の中にいかに自然に溶け込むか。
その観点から見ると、従来の「好立地」の定義は大きく揺らぐ。
この章では、その“例外の常識”をもう少し分解してみたい。
「駅前=集客」は通用しない
駅前立地は、一般的には「集客しやすい場所」とされる。通行量が多く、視認性が高く、周囲に商業施設も多い。だが、フィットネスに限っては話が違う。
駅を利用する人々は、移動中であり、目的地への通過点にすぎないことが多い。朝はギリギリまで寝ていたいし、夜は早く帰りたい。そんな生活動線のなかで「わざわざジムに立ち寄る」という行動は、現実にはなかなか起きない。
それに対して、郊外型店舗はどうか。通勤途中に自宅の近くで寄れる、休日に家族と車で移動する範囲にある、駐車場が広くて気軽に使える──こうした要素が、「通いやすさ」として機能する。
つまり、駅前は“見られる場所”ではあっても、“通いたくなる場所”とは限らないのである。
習慣化こそがすべて
フィットネスというビジネスにおいて、最も重要なのは「継続」である。
1回来て満足されても意味がない。週に1回、2回、あるいはそれ以上──習慣化されてはじめて、その顧客は“会員”となる。
この継続のハードルを決定づけるのが、「通いやすさ」だ。
それは、距離の問題であり、時間帯の問題であり、生活導線上にあるかという地理的条件でもある。
逆に言えば、いかに豪華な施設であっても、「日常に溶け込まない場所」にある限り、足は遠のく。どれだけ初期入会を促せたとしても、半年後には幽霊会員化する。
だからこそ、商圏分析の本質は“人の生活の流れをどう捉えるか”に尽きる。
地図の上で赤く塗られたエリアに、どんな生活が流れているのか。それを想像できなければ、分析などできたことにはならない。
そのヒントの一つとして、以下引用元では「現場」「現物」「現実」の三現主義について言及されており、データを頭に叩き込んだ上での話ではあるが、商圏内の特徴、テナントの利便性、地域住民の経済活動を現地で肌で感じ取り、また時には地元民しか知り得ない情報までをつぶさに拾う地道な活動も決して馬鹿にできない。
これらのインターネットサービスを用いることで、効率よく診断を行うことができます。また、実地ではわからない数値情報を得ることもできます。
しかし、これらのサービスに用いられているデータや、マップに掲載されている画像などは、リアルタイムにアップされているものではなく正確性を欠いたものとなります。例えば、夏になると街路樹に葉が生い茂って遠くから看板が見づらくなったり、画像で見るより駐車場の入口が狭くて入店しづらかったりする場合などです。
やはり、「現場」「現物」「現実」の三現主義が大事であり、机上だけではなく、実際に現場で現物を観察して、現実を認識した情報をもとに判断することが重要です。

通いたくなる施設かどうか
立地がすべて──そんな信仰に近い発想が、実はフィットネスには通用しない。
なぜなら、たとえ完璧な位置に出店できたとしても、そこに「通いたくなる理由」がなければ、人は続けて来ないからだ。
ここで問うべきは、「その施設は、わざわざ通うに値するのか?」という視点である。
設備、空間、サービス、スタッフ、価格──どれもが“通い続ける理由”として機能しているか?
この問いに答えられないまま、いくら商圏分析に精を出しても、それは“場所の言い訳”を探しているに過ぎない。
最終的に求められるのは、プロダクトの優位性だ。
立地に依存せずとも通いたくなる施設──それこそが、真に支持されるフィットネスである。
つまり、商圏分析は「場所を選ぶための道具」ではなく、「このプロダクトが活きる場所を見つけるための手段」として再定義されなければならない。
まとめ
商圏分析は、もはや「地図を塗る技術」ではない。
どんなに精緻なデータを扱おうとも、その背後にあるビジネスの構造と整合していなければ、数字はただの数字にすぎない。
特にフィットネスという領域では、常識的な立地判断が機能しない。駅前でも人通りが多くても、それが“通いやすさ”には直結しない。むしろ、生活にどう自然に組み込まれるか、心理的なハードルがいかに低いか──そこにこそ商圏の本質がある。
そして、どれほど通いやすい場所にあったとしても、通いたくなる施設でなければ意味がない。
結局のところ、「プロダクトとしての優位性」がなければ、立地もデータもただの言い訳となる。
商圏分析とは、自らのビジネスの本質を地図に映す作業である。
だからこそ、数字を見つめる前に、自分たちは何者なのかを問う必要がある。
商圏分析はマーケティング活動の一環とも言えるが、プロダクトの優位性があって初めて機能するという構図としては
こちらの記事も併せて読まれたい、マーケティング優位の蟻地獄に陥らないために。